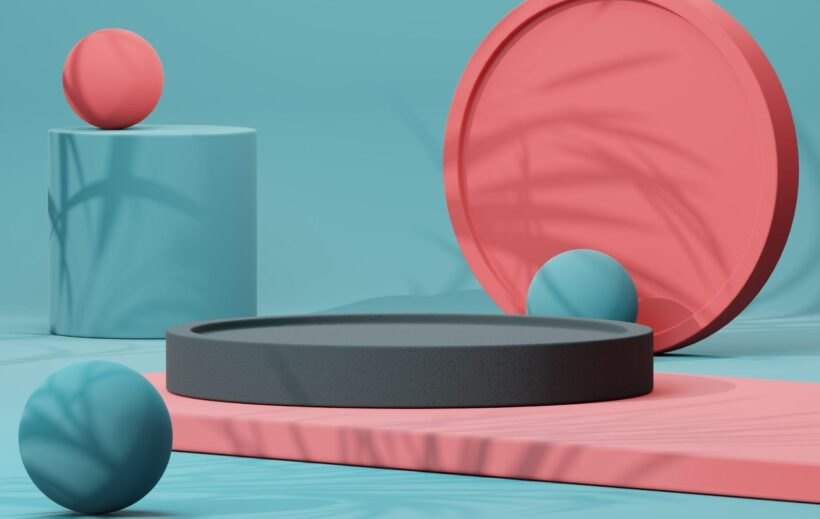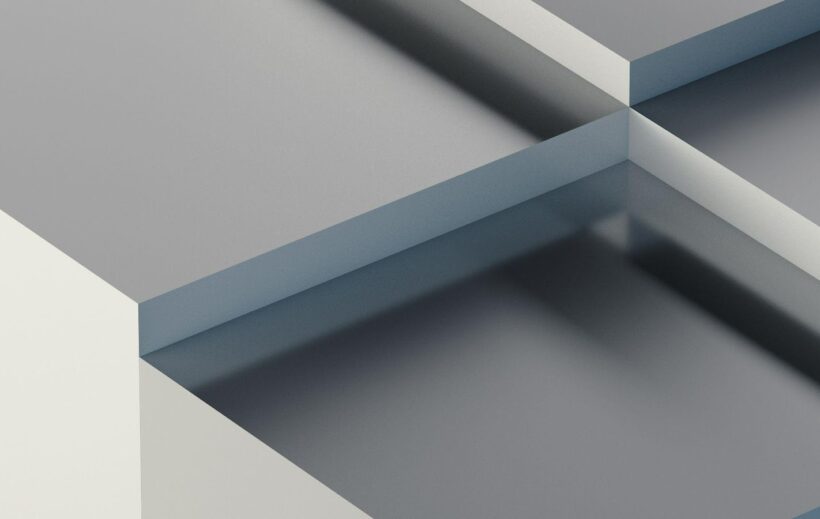Contents 目次
プロフィール

トライポッド・デザイン株式会社CEO、プロダクトデザイナー/デザイン・エンジニア/デザインコンサルタント 中川聰さん
1953年生まれ。中学校の美術教師を経て、1987年トライポッド・デザインを設立。独自のユニバーサルデザインテクノロジーや評価法を生み出す。2000年代初頭には、使い手の期待や不安にもとづく予測感性に着目したEXPECTOLOGY(期待学)を発表し、ユニバーサルデザインの第一人者として活躍。2010年、人の五感を拡張する人工感覚概念「SUPER SENSING」理論を提唱。現在、その研究の過程で発見した「超小集電」が国際的な注目を集めている。東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻特任教授(~2018年)、名古屋大学大学院医学系研究科 客員教授(2020年~)。
公式サイト:https://tripoddesign.com/
境界線に潜む本質と違和感がすべての起点
独自の理論と技術でユニバーサルデザインの普及を牽引し、東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻特任教授を務めた中川さん。元々は中学の美術教師だった。当時、素行が荒れている子供や学校にいけない子供たちのカウンセリングに奔走していたという。「親と仲良くしよう」「周りの人に優しくしよう」と説得する中川さんに、ある女子生徒が言った。
「親に生まなければ良かったと言われて育った私は、先生とは違う」
当たり前のように進学し、知識と技術を身につけて社会に出た自分と、最初の選択肢さえ与えられないまま社会に放り出される子供。そこには、歴然たる境界線があった。
「境界線はなぜ発生するのか。境界線あたりで何が起きているのか。それ以降の私は、さまざまな境界線を注意深く観察するようになりました。これが、私の原点です」

境界線は、階段や段差などの社会的障壁を乗り越えられず、日常生活や社会生活に制限がある人たちとの関わりの中で浮かび上がることもあった。
境界線の向こう側にいる人に、こちら側からどれだけの理解を示せるかは、はなはだ心もとない。むしろ不安である。しかし、中川さんは、だからこそ興味深く、追求する価値があるテーマだと感じた。やがて視点は自然にも及び、自然と人間とのせめぎあいの中にある境界線にも注目するようになる。
河川のある領域にだけ集中的に溜まるゴミ、自然の中に作られた防波堤をよじ登ろうとするツタ…。一方では人工物によって成長を阻害されているようでもあり、また一方では上へ上へと伸びる植物の性質を人工物が支えているように見えなくもない。
「境界線には、ものごとの本質があるように感じました。だから、境界線を見ることによって本質にふれている、そんな安心感も自分の中にあったんでしょう。実際、境界線を見ていて感じる『なんか変だな』という違和感が、その後のデザインにつながっていきました。違和感から気づきを得て学ぶたびに、本当に僕は何もわかっていないと思う。それこそが、僕の原動力なのです」
ユーザーの感性に寄り添った、選択肢あるデザインを追求
1987年、トライポッド・デザイン株式会社を設立。世の中は高度経済成長期以来の好景気に沸き、1人当たりGDP(国内総生産)がアメリカを抜いて世界1位になった年だ。消費の拡大を受けて、工業製品はデファクトスタンダードを大量生産する時代へと突入していた。中川さんも、会社を立ち上げるまでは「環境デザインの領域で、そうした工業社会の一端を担っていた」という。そこで、会社設立のきっかけともなる重要な境界線を見つけたのである。
「使いやすいデザインを多くの人に届けていたはずなのに、私の作った物に対して使いづらい、使う気持ちにならないという声も多く届きました。そのとき、我々デザイナーが考えている『使いやすさ』はあたかもマジョリティのようだけれど、実はもっと多様なグループに分かれているのではないかと考えたのです。デザイナーがユーザーの期待を具現化したはずのデザインによって、みずからの障がいが強調されることを嫌い、製品を敬遠する人もいる。ならば、より選択肢のあるデザインを提供するための方法を科学的に検証し、一人ひとりの暮らしをより良く変えるデザインを実現したいと思うようになりました」

口でくわえて、足の指で、穴に指を通して… 使い方に決まりなく、どんな持ち方でもしっかりグリップされるボールペン
物と共に暮らす現代社会において、誰かがデザインした物の影響を受けずに終わる1日はない。
先行的なデザインに関わってきた経験値を産業社会に活かし、”使えればいい”から”使いたい”気持ちを育むデザインを生み出したい――。
会社設立以降の中川さんは、使い勝手を追求してみずから製品を改良するリード・ユーザーが「何に使いにくさを感じているのか」に着目したユニバーサルデザインテクノロジー、またその技術と評価法を用いた企業の製品企画、公共空間のユニバーサルデザインなどに携わりながら、「ユーザーの感性にもとづく行動心理」に着目した感性デザインの研究を深めていく。
2009年には、作り手の期待・不安・失望から製品やサービスのデザインを捉え直し、新たな価値と魅力を形成する感性デザインの理論体系「期待学 / EXPECTOLOGY」を発表。作り手が期待以上の評価を想定して作り出した物が、ユーザーにとって”期待通り”のレベルに収まってしまう期待値格差がなぜ生まれるのか、ユーザーの心理を研究分析するプロジェクトを開始した。
そして今、ユーザーの価値観が多様化した現代において、モノづくりの潮流はユーザーの感動を追求する方向へとシフトしつつある。曖昧でありながら当たり前の枠組みとして存在していたものが、大きく揺らぎつつあるといえるだろう。見方を変えれば、設立当初から中川さんが取り組んできたサステナブルデザイン・ユニバーサルデザイン・インタラクティブデザインの3つが、今ようやく時代にフィットしてきたということでもある。
「当時、これらのことは特別なものとして何か隔絶されたところにありました。気づいていた人はいたかもしれないですが、時代が大量生産・大量消費を求める中で、あえて踏み出す人はいなかった。それでも僕にとっては好ましいテーマでした。ユニバーサルも、環境も、インタラクティブも、結局のところ好きだったんでしょうね」
これと決めた分野に根を張り、研究し続ける自身のことを、中川さんは「しつこい性格だから」と笑う。ふと浮かんでくる”Unusual feeling”を見落とさず、違和感を追求し続けること。失敗をするたびに、失敗する方法を学んだと前向きに捉えること。「もうダメかな、と思ったところからしかイノベーションは生まれない」と話す中川さんの生き方から、先進的な取り組みに挑むイノベーターが学べることは多い。
センシング技術の開発過程で、「超小集電」を見いだす
中川さんが大きな病気に襲われたのは、今から10年ほど前のことだ。ユニバーサルデザインを追求する過程において、視覚や聴覚などに身体的負荷を抱えている人のクロスモーダルによる五感の鋭さにふれ、人間の五感を支援拡張するために開発した人工感覚概念「SUPER SENSING」理論を提唱。彼らと共に街を歩きながら”生き延びるためのデザイン”を考えたり、”期待学”による予測感性デザイン技術を応用したものづくりを企業と進めたり、精力的に活動していたころ、東日本大震災に見舞われた。全仕事を投げ打って自分でなければできない支援活動を無我夢中で行っていたころだった。
そんな中、体調が急変した。人工心肺を使った心臓弁膜手術を受け、実に8時間も心臓が止まったままだったという。
「意識が戻ったとき、最初に薬指が動くのを感じました。日常生活で意識的に動かすことが少ない薬指に感覚が戻って、ああ、生き返ったと思った。私の感覚が拡張した瞬間でもありました」。
この日を境に、人工弁監視のためにウェアラブルの心拍計など、自らがセンサーと共に生きることになる。壮絶な闘病からの回復過程で”生き延びよう”とする自分の意思にふれ、進化したセンサーによって命がつながれていることに思いを馳せた中川さんは、日本のセンシング技術とデザインを結び付けることによって人間の感覚を拡張する「生き延びるためのデザイン」のアイデアを膨らませていった。視覚障がいをもつ人の視覚、あるいは別の感覚器官をセンシング技術によって拡張し、生きていることの実感を高めて生き延びる力を引き出すイメージだ。
「生き延びようとする力が人の五感を研ぎ澄ますこと、また五感が研ぎ澄まされることによって生きている実感が得られることを、僕は身をもって知りました。感覚を拡張することには怖さが伴うけれど、人生は確実におもしろくなる。例えば、障がいがある人にとって生きやすい形、優しい形だといわれていたものが、拡張した感覚によってそうではなくなることもあるでしょう。しかし、そうすることによって、本来の自分にとって本当に心地よいデザインを見つけることができる。世の中が示した基準を信じて暮らしていて、ふとした瞬間にそれが根底から揺らぐよりも、ずっといいんじゃないかと思うんですよ。つまり、感覚を拡張するということは、より自分らしく生きる方法を見つけるということなのかもしれません」。

退院後、中川さんは、人間の感覚や思考の拡張に注目したハードウェアやアプリケーション開発を多数手掛けた。センシング技術の開発過程で、電源がとれない地域でセンサーを動かすための手段として微生物燃料電池に着目し、2016年から微生物燃料電池によるセンシング技術を確立しようとした。
そして、思わぬ偶然の重なりから、電気化学の新たな領域として称される科学的事象に際会する。あらゆる自然物から電気を集める「超小集電(Micropower Collection)」技術の発見だった。
中川さんは、このときついた小さな灯りに大きな希望を抱き、現象の究明に没頭する。社会課題を解決に導く鍵になるかもしれない。そう直感したからである。
後編では、「超小集電」の現在地と、描ける未来について話を聞く。

超小集電の中川聰さんに聞く後編―自然から生まれる電気で世界に灯を はこちら