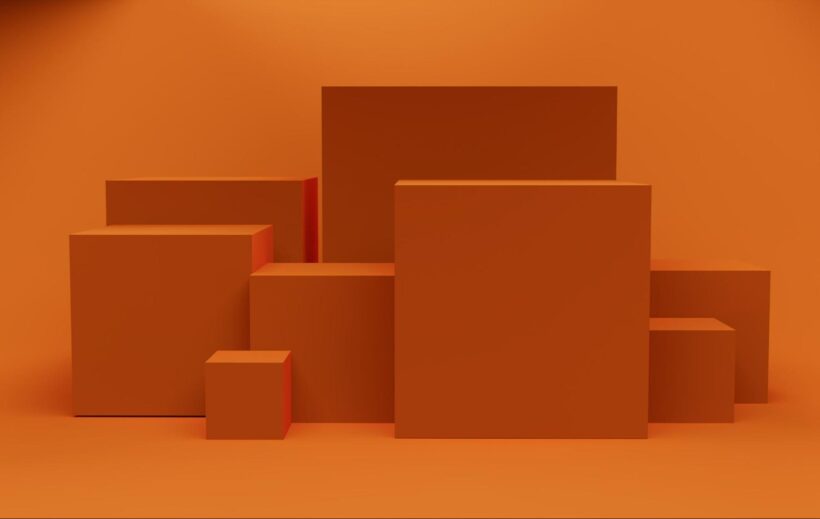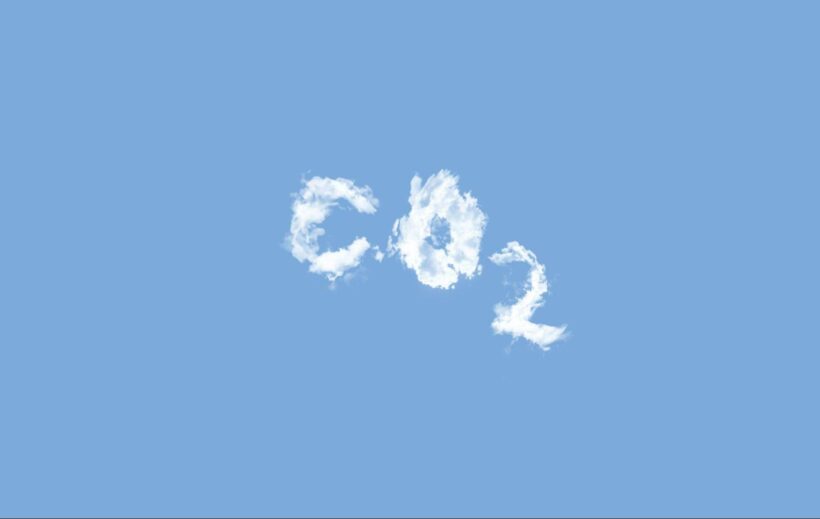Contents 目次
プロフィール

株式会社DG TAKANO 高野 雅彰CEO
水不足や環境問題を解決するプロダクト群を開発し、Red dot Design Award Best of the Bestなど多数の賞を受賞。日経ビジネス「世界を動かす日本人50」、Forbes Japan「ChatGPT後の日本の勝ち方」にも選出。日本企業の新商品開発を支援し、ディープテックやノウハウを組み合わせて、サウジアラビア都市開発プロジェクトにも参画。国際的に社会変革を牽引している。
世界の課題から逆算する事業設計
2009年、DG TAKANOは設立1年目にして「超モノづくり部品大賞」グランプリを受賞した。無電力で脈動流を生み出す節水ノズル「Bubble 90」が、大企業を抑えて日本一に輝いたのだ。
創業後にはじめて工作機に触れた高野氏は、メーカーから「素人が3年かけても無理」と言われたNC複合旋盤のプログラムを独学で習得し、わずか1年でBubble90を完成させた。「モノづくりの素人」だった高野氏が、たった1人で日本一の称号を手にしたのである。
その後も快進撃は続く。節水ノズルとは全く別のプロダクト撥水性食器「meliordesign(メリオールデザイン)」を約5年で商品化。世界三大デザイン賞のRed Dot Design Awardを受賞し、さらには食器が省エネ大賞まで獲得した。
なぜ、異なる分野で次々と世界から評価される製品を生み出せるのか──その答えは、高野氏独自の発想法にある。
「最初から世界を見ていました。日本でしか売れないものを作っても市場は限られています。世界中で売れるものを作らないと、自分の描く目標に到達しないと考えました」
高野氏は東大阪の町工場に生まれ、幼少期にバブル景気とその崩壊を経験した。技術力を誇る会社が次々と淘汰される様子を間近に見て、「技術さえあれば勝てる」という神話の脆さを痛感する。父の会社も高精度な加工技術を有していたが、時代の流れ一つで命運が左右される現実を知ったという。こうした体験を通じて、高野氏は「課題を見極め、解決策を描く力=デザイン」こそがこれからの時代に求められると考えるようになった。氏によれば、デザインとは本来「設計」を意味する。課題を見つけて解決策を導くのがデザインであり、その戦略を描くのがデザイナーの役割だ。
DG TAKANOの「DG」とは”デザイナーズギルド”の略だ。世界中からプロフェッショナルな人材が集まり、それぞれの夢をかなえるために協力し合う組織(ギルド)を作りたい――そんな思いから高野氏はこの会社を創業した。
「会社は本来、自己実現の場所であるべきです。自分の人生をどうしたいか、どう生きたいかからの逆算で、どんな会社を作り、どんな事業を作るかを決めました。そういう目標から逆算した結果です」
この逆算思考が、世界の水不足問題という巨大な課題にたどり着かせた。当時から“人類が近年直面する最も深刻な問題の一つ”とされていた水不足。水そのものは作れないが、節水なら町工場の技術でも対応できる。競合調査をすると、大企業は参入しておらず、技術レベルも決して高くなかった。しかも性能差が「節水率」という数字で明確に示せる分野だった。
「性能差が数字でわかれば、第三者的にも誰が世界一か明確になる。後発でも勝てると判断しました」
そして高野氏は、第一歩目から日本の展示会ではなく、ドイツ・ベルリンの世界最大級の水展示会に出展。最初から世界市場を見据えた戦略だった。
この思考法の根底には、「リミッターを外す」という考え方がある。「普通の道では行けない。目標設定はリミッターを外すくらいでちょうどいい」と高野氏。イノベーションを生み出すには、まず自分の思考の限界を取り払うことから始まるのだ。



技術とデザインの本質的な違い
高野氏は、日本の製造業において「技術者とデザイナーの役割が混同されている」ことを大きな課題として指摘する。
「ルイ・ヴィトンもAppleも日本企業も、みんな『世界最高のものを作る』と言っています。でも結果は全く違う。海外のハイブランドの鞄を高いお金を出して買うのは、性能が優れているからじゃないですよね。ダイソンの扇風機は数万円で売り切れるのに、3,000円でも売れ残る扇風機がある。羽根があるかないかは性能と関係ありませんし、風を送るという機能は同じです。でも20倍の価格差がある。この理由に気づけているかどうかです」
ルイ・ヴィトンは「成功者の証」を、Appleは「洗練されたクリエイティブな自分」という感情を訴求する。これが「感情設計」であり、デザイナーの仕事だと高野氏。
技術会社の視点が「自社技術を使って何を作るか」なのに対し、デザイン会社の視点は「課題をどう解決するか」から始まり、「そのために必要な技術を集める」という発想だ。
この違いが如実に表れたのが、Bubble 90からmeliordesignへの展開だった。
「普通の節水ノズルメーカーなら、次は節水の蛇口、節水のシャワー、節水のトイレと、既存製品に近い領域を作ろうとします。これが技術者視点であり、製造業の視点です。でもデザイン会社の視点は違う。水不足を解決したいなら、洗う側を極めた後は“洗われる側”の改良ですよね。だから簡単に汚れが落ちるお皿を作ったんです」
実際にmeliordesignの開発では、高野氏がコンセプトを設計し、技術スタッフに「汚れが簡単に落ちるお皿を作れる可能性のある技術を世界中から探そう」と指示。複数の企業にコンタクトを取り、共同研究開発を持ちかけた。断られることも多かったが、先進的な取り組みに関心を寄せる企業との出会いがきっかけとなり、ナノテクノロジーと瀬戸焼を組み合わせた革新的な製品を生み出した。
「技術は勝つための一つの武器にすぎません。日本は技術という武器は強い。でも武器しかないのが弱点。技術イノベーションだけでなく、異なる技術を組み合わせるデザインイノベーションが必要なんです」
技術は日本の強みであり、それ自体は揺るがない。しかし、その強みを最大限に活かすには、デザイン思考が不可欠だということだ。
本気を引き出す組織づくり
経済産業省の「日・サウジ・ビジョン2030ビジネスフォーラム」で、スタートアップ企業9社のうちの1社として選抜されたことをきっかけに、DG TAKANOはサウジアラビアの国家プロジェクトに参画、Saudi Aramco*との協力関係も構築した。多くの日本企業が同じツアーに参加していたにもかかわらず、なぜDG TAKANOだけが実際のビジネスに繋げることができたのか。
「社長が本気でやっているから。ただそれだけです」
高野氏の答えはシンプルだった。しかし、その「本気」には深い意味がある。
「人間の脳は、危機感を感じていて、かつワクワクしている時に本気を出せる。でも今の日本の多くの組織では、この心理状態を作れない構造になっています」
高野氏によると危機感とは、ピンチやチャンスを察知する“センサー”であり、それがなければ組織は変化に対応できない。だが多くの日本企業は既存事業に安住し、その結果、危機感も挑戦心もなくなっているのが本質的な課題ではないかと警鐘を鳴らす。
「中東やグローバルサウスは今から街を作る段階。チャンスが山ほどあります。世界中の企業がチャレンジしに来ているのに、日本企業だけが行っていない。危機感もワクワク感も持てない組織では、本気になれないから当然です」
DG TAKANOでは、従業員の約半数が海外出身者で、さまざまな専門性を持つ人材がプロジェクト単位で参画し、互いの夢を叶え合う文化が根付いている。世界トップ大学からのインターン生、GAFAの内定を辞退して入社したエンジニア、20代でサウジのギガプロジェクトに携わる若手、さらには大手企業出身の技術者など、国内外から優秀な人材が集まっている。
「当社は日本の会社というイメージが1ミリもありません。世界のグローバルスタンダードに合わせています。逆に、日本のサラリーマン体質が染みついている人には合わない会社かもしれません」
ビジネスの場面でも、日本企業との姿勢の違いは鮮明だ。日本では契約変更の要望が出れば「持ち帰ります」と言って新しい契約書を作り直し、数週間後に再契約となる。しかし中国企業ならその場で社長に電話を入れ、即決で合意する。欧米や韓国も、契約書に書かれていても守られない場合がある前提で、人間関係を重視しながら事業を前に進めていく。
「なぜ自分達の常識に相手を合わせようとするのか。変わるべきは自分たちの側だ」と高野氏。国をまたぐときも、時代をまたぐときも、自らが相手や環境に適応しなければ生き残れない。スタートアップにとって停滞は死を意味する。スピードとリスクを取れる決断力、相手や時代に合わせて変化する柔軟性がなければ前には進めないのだ。
*サウジアラムコ(Saudi Aramco)…サウジアラビア政府が大半を保有する世界最大級の総合エネルギー企業。保有原油埋蔵量、生産量、輸出量ともに世界最大。


技術・デザイン・ビジネスモデル 3層イノベーションで世界を変える
高野氏は、イノベーションには3つのレイヤーがあると説明する。
「技術イノベーションは、新しい素材や部品を作ること。日本人が得意な領域ですよね。デザインイノベーションは、異なる技術を組み合わせて課題を解決すること。AppleのiPhoneがまさにそうです。そしてビジネスモデルイノベーション。私たちが挑んでいるインフラ開発が、この領域に当たります」
DG TAKANOは、この3つすべてのレイヤーでイノベーションを実現している。無電力で脈動流を生み出すのが技術イノベーション、節水ノズルと撥水食器を組み合わせるのがデザインイノベーション、そして現在進めているのが中東における水インフラというビジネスモデルイノベーションだ。
「節水ノズルは上流インフラの“出口”にすぎません。世界の上流水道インフラはフランス企業が押さえていますが、下流インフラには参入のチャンスがあります。下水に流れるグレーウォーターや食品残渣を循環システムに変える——これを日本企業連合で押さえにいこうとしています」
具体的には、meliordesignの洗剤不要技術に加え、ディスポーザー技術、食品残渣を肥料化する技術、土壌改良技術などを組み合わせ、砂漠緑化まで見据えた循環型インフラの構築を構想している。
「グローバルサウスは今から街を開発します。一方でアメリカ、中国、オーストラリア、インド、アフリカ、中東も砂漠化が進んでいる状況で、砂漠を緑化できる技術は日本企業連合にある。あとはスケールアップのための資金が必要なのです」
環境問題への関心が高いアメリカやドバイで資金を集め、一気にインフラビジネスを展開する計画だ。この壮大な構想は、DG TAKANO一社だけでは実現できない。世界の水不足解消に向けて、日本企業連合としても世界に挑んでいく。
日本製造業の未来への提言
では、DG TAKANOの歩みを踏まえた上で、今後の日本の製造業――特に新規事業を牽引するビジネスパーソンや経営者は、どのようにイノベーションを起こしていけばいいのか。高野氏に、そのための指針を聞いた。
「まず、自分が何者になるかを決めることです。技術者なら技術イノベーション、デザイナーならデザインイノベーション。それぞれのポジションで起こせるイノベーションの種類が違います」
そして最も重要なのは、「既存の延長線上にイノベーションはない」という点だ。
「常識外の判断・戦略・行動を取らない限り、イノベーションは生まれません。頭では理解していても、実際にできる人はごくわずかです。人間という生き物は、危機感がなければ本気で新しい挑戦などできないからです。だからこそ、自らリミッターを外し、安全圏から一歩踏み出さなければ始まらないのです」
高野氏は、技術力という強みを最大限に活かすための新しい視点を提示した。
「技術力は大切です。でも技術だけでは勝てない時代です。デザイン会社と組んでください。上流のデザイナーと協働することで、技術の価値を最大化できます」
東大阪の町工場から始まり、世界の水問題に挑むDG TAKANO。その軌跡は、日本の製造業が秘めるポテンシャルの大きさを示している。必要なのは、技術力という強みにデザイン思考という新たな武器を掛け合わせること。そして何より、世界を変える本気の挑戦と覚悟だ。