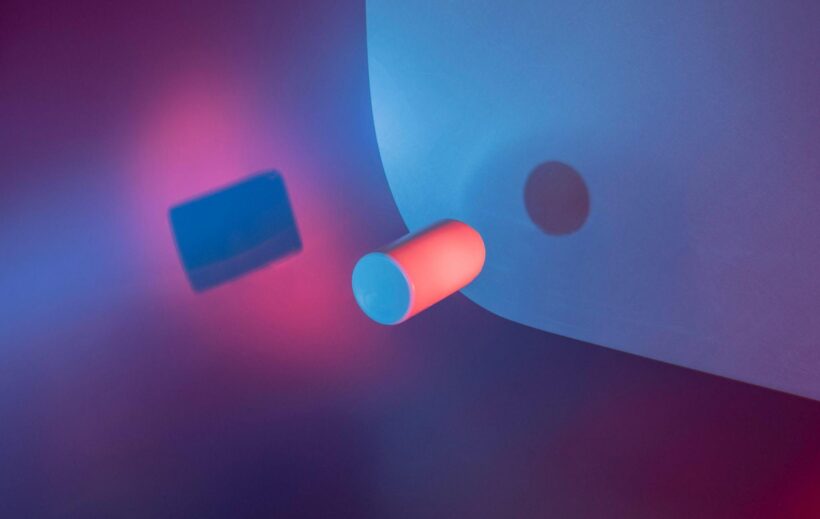Contents 目次
プロフィール

みずほフィナンシャルグループ 執行役員CBDO 中馬 和彦氏
KDDIのオープンイノベーションの事業責任者としてスタートアップ投資や新規事業を手がけ、「イノベーティブ大企業ランキング」では7年連続1位を獲得。2025年からみずほフィナンシャルグループ執行役員CBDOに就任し、グループの新規事業統括に携わる。「新しい資本主義実現会議」スタートアップ育成分科会委員、経済産業省 J-Startup推薦委員、経団連スタートアップエコシステム変革TF委員、東京大学大学院工学系研究科非常勤講師、一般社団法人Metaverse Japan理事、株式会社PARTYエクゼクティブアドバイザー、他多数。
次の10年は、ルールを“待つ側”から“作る側”へ
今や、私たちの生活に欠かせない存在となったインターネット。平成の始まりとともに黎明期を迎えた巨大な情報通信網は、コミュニケーションの在り方を一変させ、消費・購買行動や産業構造に劇的なブレイクスルーをもたらした。
だが、当初からその社会的インパクトが十分に見通されていたとは言いがたい。
とりわけ日本では、インターネットの本質的な価値を早期に産業や経営に結びつける動きが遅れた側面がある。その結果、平成という時代──すなわち「失われた30年」と重なる長期停滞期のあいだに、世界の先進国がデジタル技術を梃子に新たなイノベーションを創出していく中で、日本企業は従来型の価値観や組織構造から抜け出せず、競争力の面で後れを取ることになった。
KDDIで多くのスタートアップ投資や新規事業を手がけ、オープンイノベーション活動を統括した中馬和彦氏も、ガラケーからスマホへの変遷において自社の衰退を見たひとりだ。
2000年代初頭、日本の携帯電話市場は世界でも突出した存在だった。カメラ搭載端末やワンセグ視聴、音楽再生、非接触ICカード(おサイフケータイ)など、今のスマホに通じる多機能端末を次々と実用化し、技術的には“世界最先端”と称されていた。しかし、その独自進化はやがて「ガラパゴス化」と呼ばれる閉じた構造につながり、国際市場での競争力を弱める結果となる。AppleやGoogleといったIT企業が共通OSとアプリエコシステムを武器に主導権を握ると、競争地図は一気に塗り替えられた。
「世界を牽引していた日本が変わっていく過程を目の当たりにしました。現役で事業を担っている最中に、会社の隆盛が一気に過去のものになる。この経験から得た危機感が、新規事業創出に挑む原動力となったことは間違いありません」
そしていま、AIの登場によって、歴史は繰り返されようとしている。AI需要で半導体市場のシェアが大きく変わったように、AIが各分野の融合・再編を促す兆しを感じている人も多いだろう。中馬氏も、インターネット黎明期を彷彿とさせるAIの台頭こそ次のパラダイムシフトであり、「今が備えるべきタイミング」だと話す。
「AIがさらに進展すれば、インターネットが登場したときに起きた世の中のガラガラポンみたいなものがもう一回来るでしょう。しかし、それが起こる前に行動を起こすことができれば、産業の主導権を握って勝ち切れることを歴史は語っています」
日本が再び同じ轍を踏まないために、自分はどこで何をすべきかーー。
中馬氏は熟慮した結果、融資や出資を通じて産業全体に関与し、産業横断的な仕組みづくりで日本企業に勝ちをもたらすことができる金融業界への転身を決めた。2025年より、みずほフィナンシャルグループに活動の軸足を移し、CBDOとして新規事業の創出や市場開拓を通じて企業の成長戦略を牽引している。



中馬氏が考える、製造業におけるイノベーションの課題
競争環境が変わる潮目を見極めることは、製造業のイノベーションにおいても重要なポイントだ。戦後復興から高度経済成長期を経て、日本は自動車・家電・半導体といった分野で「Japan as Number One」と称された時代を築いた。しかし、グローバル化とデジタル化の波、そして新興国の追い上げに十分に適応できず、とくに家電や半導体では存在感が大きく後退した。
背景にあるのは「ハード偏重」の産業構造だ。高品質なものづくりを強みにする一方で、ソフトウェアやサービスによる価値拡張では欧米やアジア勢に後れを取った。多くの家電メーカーや通信機器メーカーがスマートフォンへの転換で競争力を失ったことは、製造業のイノベーション課題を象徴している。そのなかで、現在もグローバルブランドとしてスマホ事業を継続できている日本企業はソニーのみである。
では、ソニーは他の製造業と何が違ったのだろうか。
他のメーカーがハードウェア主導・組み込み型にとどまるなか、ソニーはPlayStationやPC事業、音楽・映像コンテンツなどを通じてソフトウェアやサービスの発想を取り込み、Android陣営のエコシステムにも適応した数少ない企業だった。その結果、「ハード・コンテンツ・ソフトウェアの融合」によって事業継続に成功したのである。
「最終製品をつくって終わり、という製造業的発想で止まらず、“顧客に使われ始めてから関係性が始まる”というサービス的な感覚を持ち込めたことも、ソニーが勝ち残った理由のひとつではないでしょうか。今やソニーを家電メーカーというイメージで見ている人は少ないでしょう」
「SDV(Software Defined Vehicle)」が自動車産業の新たな方向性として注目されるように、これからはソフトウェアがハードの進化を牽引していくのは明らかだ。AIの進展によって工場の自動化や無人化が加速すれば、ものづくりは単体産業ではなく、他領域との接続やサービス化を前提とした構造へと移行していくだろう。
日本の製造業はこれまで、「歩留まりを上げ、品質を安定させること」を何より重要視し、その強みで世界を牽引してきた。しかし、最終製品をつくって納品すれば役割が終わるという発想のままでは、価値がソフトウェアやサービスへ広がる時代には対応しきれない。AI時代の主導権を再び他国に奪われないためにも、従来の強みを前提にしながら、自前主義や業界の枠を越えて“異質なもの”と組む勇気が求められる。
異質なものとの交わりを成果につなげるコツ
異文化との共創によるイノベーションに取り組む場合、「異なる思考やロジックをいかに共存させるか」が課題になることが多い。単発のプロジェクトで終わらせないために、中馬氏は「現場の自走」「ダブルスタンダードの許容」「長期分散投資」の3つを意識して環境を整えることが重要だと話す。
「創業者や社長が『新規事業は俺が旗振りするぞ』と先頭に立つケースは、たいてい失敗します。一方、適切なトップダウンで現場が走れる環境を整えてから、権限を委譲して現場が自走する仕組みを整えた場合は、成功する確率が高い。異質なものと交わる仕組みまではトップダウンでつくり、そこから権限を委譲することによってイノベーションが生まれやすい風土をつくるのが理想的です」
現場主体のイノベーションを推進する有効な手段として、中馬氏は「ベンチャークライアントモデル」を挙げる。ベンチャークライアントモデルとは、大企業がスタートアップの顧客となって技術や発想を吸収し、自社の課題解決と経済的効果の達成につなげるオープンイノベーションの手法だ。BMWが開発したこのモデルは、多くの成功例を生んでいる。
名古屋にある、Tier1サプライヤーもそのひとつだ。米国で学んだ2代目社長がベンチャークライアントモデルの導入を提案したが、熟練工の反発に合って頓挫。それでも「一人あたり500万円で、必ずトライするように」と強制的に予算を割り振ったところ、自分たちとは異なる視点やアプローチに触れることで現場の心が動き、「この会社と組んでみたい」「この技術を取り入れたい」といった自発的な動きにつながった。自社にない視点、思想と関わることで道がひらけ、トップダウンからボトムアップに移行することによって成功した好例として紹介した。
しかし、安定志向でリスク回避の傾向が強い大企業では、せっかく生まれた新規事業に既存事業側が拒否反応を示すことがある。確立された収入源である既存事業とのミスコミュニケーションが起こることを懸念した結果、新規事業が停滞するケースは多い。
「品質を守る、リスクを減らすといった安定志向の論理で動く既存事業に対し、新規事業はスピードを優先し、失敗から学ぶ探索志向の論理で進みます。そもそも性質と思想がまったく違うので、両者を無理にあわせようとするのは得策ではありません。壁を壊すことより、権限を適切に委譲して組織に余白をつくることが大事。バックオフィスを含めて会社全体でダブルスタンダードやトリプルスタンダードを許容し、二重構造の経営を支援できる体制をつくることができれば、自然にイノベーションは生まれます」
一本足打法ではなく、複数の領域を並走させる長期視点がポイントだ。
「成果を出すには、裁量・責任・スピード・時間軸――この“権限の面積”が必要なんです。“1点集中で、1年で成果を出せ”と言われてもそれは難しい (笑)新規事業っていうのは“資産”なんですね。本来は投資と同じで、ある程度まとめて預けて、時間をかけて育てる。リスクの高低を考えて異なるセクターやテーマに投資し、全体の収支に与える影響を最小限に抑えつつ、蒔いた種のいずれかが芽を出すのを待つくらいの感覚がちょうど良い。事業となるとテーマを絞りがちですが、考え方は、“長期で分散”個人の資産運用と同じです」

“横断のハブ”として「信頼のネットワーク」をつくり、産業の未来をつなぐ
中馬氏は、「出口視点」を持つプレイヤーを間に入れ、市場側の文脈で技術を評価する重要性を指摘する。たとえば、サプライチェーンの知見を持つ商社や金融機関は、技術を市場につなぐ“翻訳者”として機能し得る存在だ。
製造業のように技術ドリブンな組織では、「技術的に優れているものをつくること」自体が目的化してしまいがちで、顧客側の価値基準での評価や選択が遅れやすい。一方で、商社や金融は、市場ニーズ・価格・採算性・規制・現地事情といったリアルな視点から「社会実装における出口戦略」を描くことができる。こうしたプレイヤーが介在することで、研究・開発のフェーズにある技術も「どこで・誰に・どう価値化できるのか」を具体的に見立てられるようになるのだ。
一方で、かつてのように産業ごとの“縦のバリューチェーン”の中でビジネスを組み立てるモデルも、その機能のあり方が変化しつつある。従来、商社は原材料・製造・物流・販売を垂直的につなぎ、各業界の枠組みの中で効率性を高めることで価値を発揮してきた。この強み自体は揺らいでいないものの、産業の境界が再編される現在においては、役割の広げ方や関わり方にも新たな形が求められている。実際、商社各社も「事業投資型」「事業共創型」への展開を強めはじめている。
例えば、自動車メーカーがソフトウェア産業に踏み込み、電力会社がエネルギーデータの利活用に動くように、産業はもはや“縦割り”では成立しない。だからこそ、商社・金融・アカデミアのような「中立性・ネットワーク・資本力を持つプレイヤー」がハブや触媒として機能する価値はむしろ高まっている。
実際に、海外では金融機関・投資ファンド・知財投資会社などが、資本を通じて産業横断型の影響力を強めている。中馬氏も、金融の役割を「お金を貸すだけではなく、業界の垣根をまたぐネットワークそのものを提供できる存在」と位置づけ、商社を含む既存プレイヤーとともに“産業間をつなぐ立ち位置”に可能性を見出している。
「金融業が触媒となって信頼のネットワークみたいなものを作れたら、異分野を組み合わせた事業、あるいは産業をつくることも不可能ではありません。これまでとは次元が違う新しい価値を世の中に提供できる未来を、いま妄想しているんです」
みずほフィナンシャルグループは、これまでにもスタートアップや革新的サービスに出資するCVC、新規事業開発に特化したインキュベーション組織などを積極的に立ち上げ、金融の枠を超えたビジネスの創出に挑んできた。既存の秩序が崩れるとき、金融業が産業の交差点として生み出す信頼のネットワークが機能すれば、異なる才能や技術の交わりによって想像を超えるイノベーションが生まれる可能性がある。
各産業のイノベーターにとって大切なのは、迫る変化を価値創造のチャンスと捉えて環境整備に取り組むことだ。次の10年に向け、文化として「異質を受け入れる」準備を進め、AI時代の新たな秩序づくりに加わるチャンスをつかみたい。